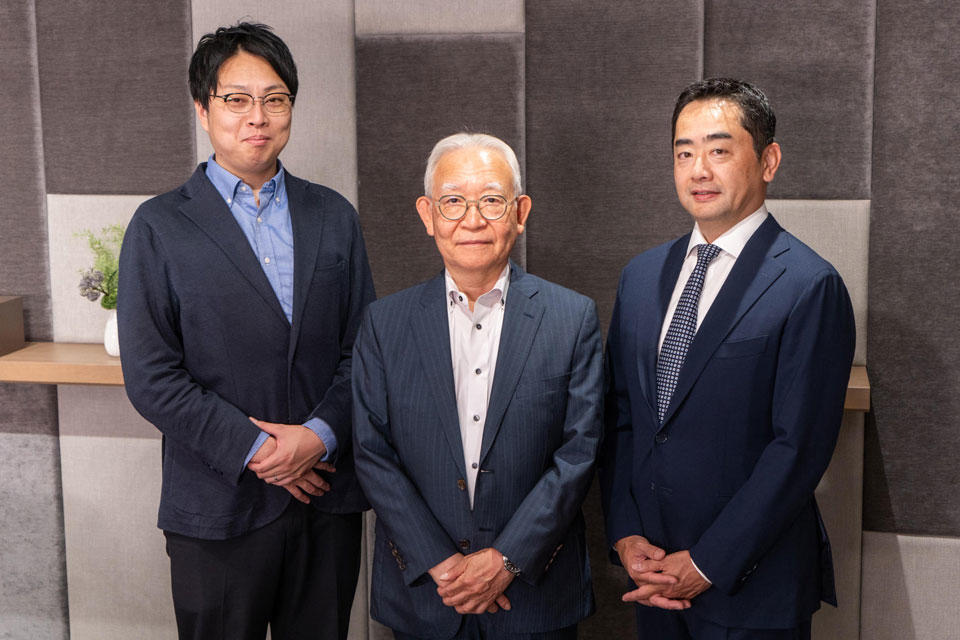Management Issue Vol. 6
日本的経営の今後と経営のあり方


岩尾 俊兵氏
慶應義塾大学商学部 准教授
慶應義塾大学商学部准教授。平成元年佐賀県生まれ、慶應義塾大学商学部卒業、東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了、東京大学史上初の博士(経営学)を授与され、2022年より現職。著書に『イノベーションを生む“改善”』(有斐閣、第73回慶應義塾賞、第37回組織学会高宮賞、第22回日本生産管理学会賞)、『日本“式”経営の逆襲』(日本経済新聞出版)、『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)など。
MSOLのミッションは「Managementの力で、社会のHappinessに貢献する」こと。では、どうすれば社会のHappinessに貢献できるのか、あるいは、Managementの力をどのように活かせばHappinessを実現できるのか。一流の有識者に独自のポジションから意見を伺う7回目の対談は、慶應義塾大学商学部准教授の岩尾俊兵氏をお招きしました。今回は日本的経営の今後と経営のあり方をテーマに弊社代表(※取材当時)の高橋と語っていただきます。
学生であれ、大人であれ、どんな人にも
マネジメントが身近なものであってほしい
高橋
岩尾先生とのご縁は先生の御著書『日本"式"経営の逆襲』(日本経済新聞出版)を拝読して私が興味を持ったことがきっかけです。先生は新進気鋭の経営学者の1人として現在ご活躍中ですが、そんな先生がこの度『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)という御著書を新たに刊行されました。中高生から経営を学ぶべきだというのは私も共感するところですが、くしくも私と岩尾先生の共通項は父親が経営者であったことです。経営者がいる家庭環境の中で、幼い頃から知らず知らず耳にして身に付けた見方、考え方があるかと思いますが、なぜ今回中高生向けに本を書こうと思われたのでしょうか。
岩尾
そもそも「経営」は起業家だけのものではありませんし、社長になるためだけのものでもありません。会社員、あるいは芸能人や小説家などどんな職業に就くとしても、この「経営」=マネジメントができるようになると成果が得やすくなるのです。もし成果を得られない場合でもマネジメントの勉強だと思えば、次の機会に成果を得られやすくなります。アメリカでは企業の創業ファミリーやMBAホルダーのエリートといった一部の社会階層にマネジメントの知識やノウハウが集中しているように見えます。それに対して、日本では会社の中でトップから組織の末端に至るまで、日本的経営、日本式経営が育まれてきた歴史がある。そうしたマネジメントの知識やノウハウを社会全体に解き放ちたい。そう思ったのが執筆のきっかけです。
高橋
今から10年ほど前、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』(ダイヤモンド社)という本が大ベストセラーとなりました。それだけ日本社会ではマネジメントに対する関心が高いのかもしれません。マネジメントは組織に属している個人が組織という観点から組織をマネージしていくというものです。今は組織に対する同調圧力が強すぎて、マネジメントを主体的に行っていくという観点が薄くなっているように見えます。しかし、今後マネジメントを学んでいくうえで、この本は日本社会に眠っている有用な社会的、文化的要素を喚起させるのではないか。
実は、先生に刺激を受けて、私たちも中高生向けにマネジメント教育を行っていきたいと考えているんです。MSOL(エムソル)はプロジェクトマネジメントの専門会社です。そのノウハウを例えば文化祭や運動会などにも活用してほしい。マネジメントは自分たちに身近なものであるということを中高生に理解してほしいのです。
岩尾
今、政府を始めとして若年層に起業家教育を推進する気運が高まっています。実際に私の周りでもマネジメント塾のようなものをつくりたいと思っている会社や個人が少なくありません。それだけマネジメントに対する社会的ニーズが高まっているのでしょう。
日本ではマネジメントのプロフェッショナルが圧倒的に少ない
高橋
私も個人的にベンチャー支援を行っていますが、アイデアや商品、技術をどのようにビジネスとして仕立てていくのか。実はそのとき大事なのは「人」なんです。人を採用するだけではなく、どう組織をつくっていくのか。ただ、こうしたプロセスを組み込んで、しっかり組織をマネジメントしていくためのスキルを持っている人が日本では圧倒的に少ないように感じています。会計やマーケティングなどの専門家はたくさんいますが、それらを束ねて組織をマネジメントできる専門家はまだまだ少ない。
一方、アメリカではマネジメントの専門家がたくさんいます。そのため、アメリカは起業したあと、創業者は次の経営者にバトンタッチしやすい。例えば、グーグルの経営も創業者からマネジメントに長けた専門経営者に引き継がれ、大きな成長を遂げました。
そうしたプロフェッショナルがアメリカにはたくさんいますし、彼らは働きにふさわしい評価も受けます。しかし、日本ではマネジメントの専門家が評価される土壌がない。まるで会社で出世した先にマネジメントがあると思っているようです。本来、マネジメントは技術であり、スキルであるはずです。プロフェッショナルとしてのマネジメントの存在感は日本では圧倒的に薄いと言わざるを得ません。
岩尾
確かにそうですね。マネジメントは1つのプロフェッショナルであるべきものです。だから、私はこう考えるんです。もし組織のトップから末端まで全員にマネジメントの素養があれば、その会社はとても強い会社になるだろうと。これから社会全体がマネジメントマインドを持つようになれば、もっと多くの人が幸せになると思っています。
高橋
ただ、組織に従っていくことが美徳とされるような教育を受けてきた世代に、いざ主体的にマネジメントをしなさいと言っても、なかなかできるものではありません。日本では高度経済成長時代に旨みを得た世代が社会をリードしてきましたが、その下の世代は、自分のキャリアをどう築いていけばいいのか、どう稼いでいくのかといった主体性に乏しいように見えてしまうのです。

岩尾
世界の起業家数ランキングを見ると、当然ながらアメリカがトップクラスに入ると思われるかもしれませんが、実際にはイメージとは異なり、南米やアフリカの国々が上位に入ってきます。それは起業しないと他に稼ぐための選択肢がないからです。
他方、日本では起業しなくても、働ける企業がたくさんあります。就活さえ突破すれば、どうにか生きていける。いわば、就活が現状の部分最適解となっているのです。起業をする必要もないし、マネジメントマインドも持たなくていいと考える人が少なくないのです。しかし、そんな考えを持った人たちばかりが企業に集まってしまえば、どうなってしまうのか。今ある大企業も、かつて誰かがつくったものです。これからも将来大企業になるような企業がどんどん生まれていかないと、日本全体が沈んでしまうし、皆が不幸になってしまいます。
若い世代は魂の燃やしどころをいつも探している
高橋
私が学生時代を過ごした90年代から学生が大企業を目指す傾向は変わっていません。その根本的な問題なのか、いつも考えるのですが、その1つに家庭内教育が影響しているのかもしれません。ちなみに私の子どもたち(息子22歳、娘17歳)には10歳を過ぎた頃から、「義務教育は中学までだから、それ以降、どう稼ぎ、生きていくかは自分で考え、そのために必要な高校、大学を選びなさい」と言っていたのですが、大事なことは手段を目的化しないことです。多くの親御さんは子どもが大学に入学することがゴールだと考えていますし、子どもたちも良い大学に入れば、大企業に入れると思っている。そうすれば人生安泰だというわけです。
岩尾
しかし、すでに大企業に入れば人生安泰だという時代は終わりました。それを何となく親も子どもも感じ始めているように思います。大企業でもいつ崖っぷちに立たされるかわからないという今の状況を冷静に見れば、もっと危機感も強くなるはずです。危機感があれば、人は勉強します。そんなときこそ、マネジメントを勉強すればいい。人は誰でも自分の人生の経営者です。そう思ったほうが人は幸せになれる確率が高くなるのです。
高橋
極端な言い方かもしれませんが、今回の御著書は「ノアの箱舟」のようなものになるかもしれませんね。日頃、有識者の方々と話していると「日本が変わるには、一度堕ちるところまで堕ちないとダメだ」という話になるんです。大洪水が来ないと変わらない。
先日、6年ぶりにニューヨークに出張に行ったのですが、アメリカの社会はダイナミックに動いていることを実感します。むろん格差という問題はありますが、鮮やかに社会が変わっていく側面がある。それに対して、日本はあまりにもダイナミズムがなさすぎる。今回の先生の御著書はこれから若い世代が古い世代と世代間闘争をするときの大いなる武器になるかもしれませんね。

岩尾
日本が変わっていくには、誰かが情熱を持って点火しなければなりません。若い世代は魂の燃やしどころをいつも探しています。これまで日本では1つの組織に入って長くいることが良しとされ、40~50代で初めてマネジメントを学べる役職につくというケースが一般的でした。そのため、マネジメント能力を身に付けるまでの時間が非常に長かった。
しかし、今回の私の本は、若い世代でも時間を短縮してマネジメントを学ぶことができるものだと思っています。ぜひ一度手にとって読んでみていただきたいですね。
日本企業は各人の評価に差をつけないようにしがち
高橋
日本では新卒採用が当たり前ですが、本来企業経営において新卒採用は非合理的なものです。育成する教育投資の負担が大きいからです。例えば、中国では若年失業率がコロナ禍の影響もあり20%近くとなっており、アメリカでも新卒で大学を出ても、就職先探しに非常に苦労すると言われています。
新卒の世界的な環境からすると、日本は非常に恵まれています。ただ、新卒採用は学生と企業がお互いに暗闇の中で握手しているようなもの。企業は就業経験の無い学生の何かを見抜き、学生は企業をイメージして選ぶ。そこから3年くらい経って、お互いに現実をようやく知るようになります。
私の会社では、3年ともに働いて、もし自分のキャリアを他で活かしたければ、会社を辞めてもいいと言っています。ただし、3年は働いてほしい。こちらにも投資したリターンを返してほしいし、本人にも仕事のノウハウが身に付かないからです。
岩尾
今の学生は昔のように銀行や商社に入りたいという感じではなくなっています。もちろん人気の業種が変わってきていることもありますが、最近はベンチャー企業で鍛えてもらいたいという学生もどんどん増えています。大企業に入るにせよ、ベンチャーに入るにせよ、働き先の多様性が拡がっていくことはいいことだと思います。
高橋
日本ではアメリカと比べ、機会の平等については良い面があるのかもしれませんが、結果の平等というときに、結果に対してきちんと評価をするという制度やプロセス、あるいは意識がまだまだ足りていないと感じています。私もかつては外資系コンサルで働いていましたから、結果について評価するときの目は厳しい。もちろん厳し過ぎてもいけないのですが、日本では各人の評価に差をつけないようにしがちです。それが日本企業の根本的な問題点なのではないかと考えているのですが、どうでしょうか。
岩尾
最近、私が見た大学生に関する意識調査では、優秀な子でさえ評価されて特別扱いされるのがイヤだという調査結果が出ています。周囲から目立つことは勘弁してほしいというわけです。褒められること自体は好きだが、皆の前で褒められたくないのです。
一方、私が所属している大学では、そんな話をしてもピンとこない学生が少なくない。皆の前で褒められたら、うれしいと言います。二極化しているのかもしれませんが、全体としては評価されてあまり組織の中で目立ちたくないという人が多くなっているのでしょう。
大陸国家と海洋国家の違い
日本社会で育まれたものとは何か
高橋
実は私も目立ちたくないんです。内向的な性格なので、人付き合いが苦手ですし(笑)。ですので、目立ちたく無いから人前で評価されたく無いという気持ちも理解できますが、組織に対する貢献意欲を高めるためにも評価は必須だと思います。アメリカや中国ではひとりひとりがきっちり評価されます。評価されることが自分のモチベーションにつながっていくからです。
岩尾
今の大学生は小中学生時代に「ゴールは一緒に」「皆が素晴らしい」というような教育を受けたから、そうなっているという話もあります。日本は昔から平等配分が好きなのですが、ここ数年でその傾向が非常に強くなっているように感じます。
高橋
歴史的に見ると、昔の狩猟民族は結果に対して皆平等であることを重視していました。狩りに行っても分け前を平等に分けていたからです。それが農耕民族になって差をつけるようになった。そこから闘争が生まれ、大きな戦争になっていった。日本は縄文時代の狩猟民族のプリミティブなものを残しつつ、社会が構築されてきたのではないか。大陸である欧州では文化が衝突してきた歴史がありますが、日本は島国であるがゆえに、そのまま残されてきた。組織の中で、個が際立って評価されたくないということも、そうした歴史が影響しているのではないかと思います。
岩尾
社会人類学者である中根千枝氏は自著の『タテ社会の人間関係』(講談社)の中で、そうした日本的経営の特徴をきれいに分析されており、多くの人にも読まれました。ただ、タテ社会というのは、ヨコのつながりがない社会とも言えます。
例えば、アメリカではMBAを取得して、いくつかの企業で経営層の一員となって経験を積みながら、トップに到達するコースを歩みます。1つの組織だけではない複眼的な視点でマネジメントを学ぶことができるのです。しかし、日本企業はそうではない。マネジメントのプロフェッショナルを育てる多様なコースが存在しない。だから、マネジメント人材もなかなか育たないのです。
理論的な裏付けや指導的な立場をもった 経営学者がこれからもっと出てきてほしい
高橋
確かに今、日本の企業にマネジメントのプロフェッショナルが足りないということが大きな課題となっています。だから、コンサル会社が重宝される。日本の大企業は自社内でプロフェッショナルを育成することができていないからです。
そうした状況の中、ジョブ型雇用が生まれたのですが、本当に企業は活用して評価できているのか。非常に疑問です。どうすればもっと日本の経営を改善できるのか。それには経営学が貢献すべきです。経営者は常に悩んでいます。欧米流のマネジメント手法と日本的な組織文化との折り合いをどうつけていくのか。そこに大企業が腐心している。そんなときこそ、経営学者の出番なのですが、日本では今、経済学者と比べ、経営学者の存在感が小さいように見えます。
岩尾
「経営学者はいらない」。そう言われることがよくあります。経営者が話せば済むことだからと。確かにそうかもしれません。ただ、1人の経営者の体験やノウハウを多くの人たちの間で共有するには、抽象化するとともに、本当にそれが正しいのかどうかを他の事例と比較して検証し、普遍的なものを抽出する必要があります。その点において経営学者は貢献できると思っています。
高橋
私は経営学の本を読むときは、何度も読んで、よく読み込まなければ理解できないようなレベルのものを読むことが好きです。例えば、ピーター・ドラッカーの本などはそうかもしれません。経営者は本当に抽象化された経営学を必要とします。それを具体的にどう落とし込んでいくかが経営者の仕事だからです。
しかし、私がこれまで読んできて有益だと思う経営書のほとんどは輸入モノです。アメリカの経営学はアメリカのビジネス社会の中で生まれたものです。その意味で言えば、日本でも日本の社会、風土の中で培われ生まれる経営学があってもおかしくないはず。なのに、なぜか輸入モノばかりありがたがってしまう。そうした風潮に疑問を感じるんです。
岩尾
もともと日本には素晴らしい経営学者がたくさんいらっしゃいます。本も読まれていますし、社外取締役になっている方も少なくありません。他方、アメリカではビジネスパーソンが読むような本を書いている経営学者はほとんどいませんし、社外取締役になっている学者もほとんどいない。アメリカではアカデミックな世界でジャーナル(論文)競争をしている経営学者が評価されており、日本とは経営学者としての評価やスタイル、生き方が異なるのです。私は高橋さんがおっしゃるように日本の経営学者として、これまで先人たちが築き上げてきた知見をさらに進化させて、新たな経営コンセプトを世界に向けて発信していきたいと考えています。
高橋
私は経営学者を応援したい。自分が読んで、感動するような本を書く書き手がもっと現れてほしいと思っています。例えば、日本の企業における評価とは、どうあるべきなのか。もしかしたら結果の平等を重視し過ぎるがゆえに、育つべき人が育たないのではないか。評価についても定量的な情報に限らず、定性的な部分も含めて評価すべきではないか。実際、私たちの会社では評価についてお互いに納得するまで多くの時間を割いています。こうした理論的な裏付けや指導的な立場を経営学者が担ってほしい。その意味でも、今後の岩尾先生のご活躍をぜひ期待しております。

(対談日:2022年6月29日)
MSOLの特長をもっと知る
MSOLをより詳しく知っていただくためのコンテンツを揃えています。
-
MSOLのミッション MSOLのブランドやミッション、今後の展開についてのビジョンなどをご紹介します。

-
ブランドパーパス MSOLブランドの持つ大切な意義、目指すところを示した、ミッションビジョンを達成するためのブランドストーリー

-
MSOLのマネジメント SDGsを始めとしたマネジメントの論点(Issue)を各界の有識者と探求し、その答えを紐解いていく。

-
ストーリー MSOLをより理解していただくために、働く社員それぞれのインタビューをご紹介します。

-
グループ会社 グループ会社についてご紹介します。グループ企業のシナジー効果により、高いプロジェクト成功率を誇ります。

-
書籍・記事紹介 MSOLファウンダーの高橋の書籍や、雑誌などのインタビュー記事をご紹介します。

MSOLについてもっと知る
自由度が高く
自由度が高く
いつでもチャレンジでき、
裁量権を持って働ける職場です。
お問い合わせはこちらから
MSOLへのご相談やご質問については
こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせください。